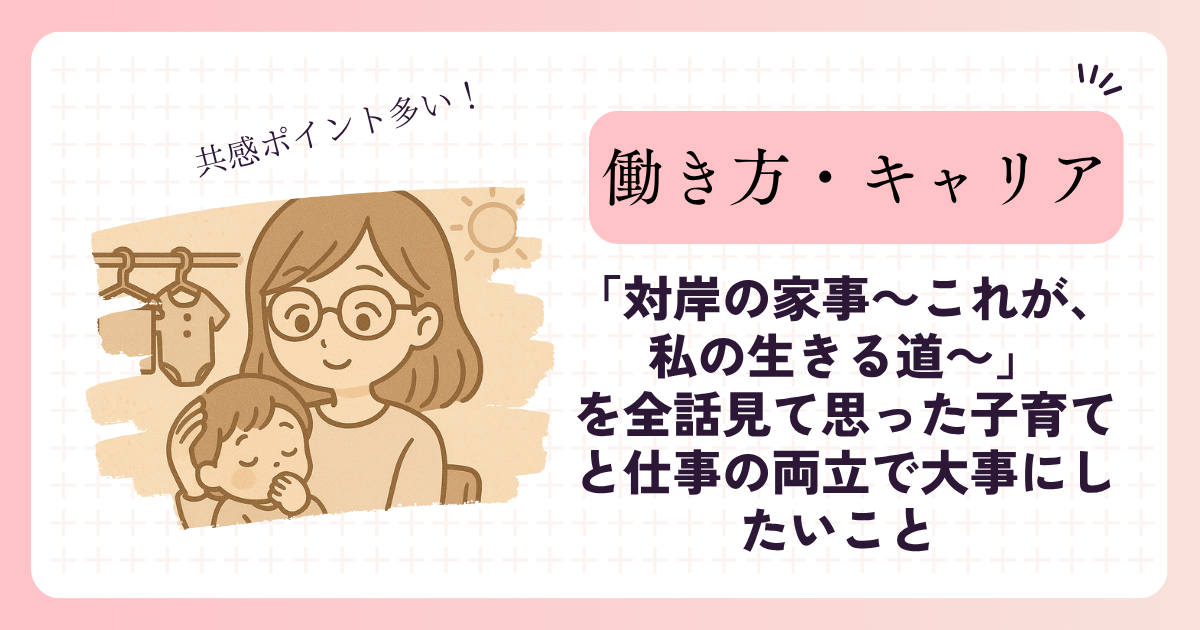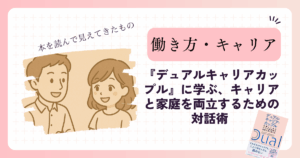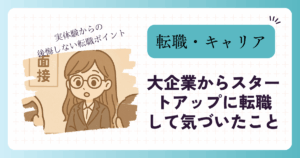ドラマについて
TBS系 2025年4月ドラマ 「対岸の家事~これが、私の生きる道~」」が子育て世代は共感の嵐!? 是非見ていただきたいドラマです
ドラマの紹介
- ドラマ:専業主婦の多部未華子さんが演じる村上詩穂を中心に、周りの人間関係から日々の現代の家事や育児の負担、夫婦の役割分担、社会の認識のズレをリアルに描いた作品です。
- タイトル 対岸の家事~これが、私の生きる道~ 放送局/配信サービス TBS系(現在は放送終了)/U-NEXT 放送日時 毎週火曜22:00〜 話数 全10話 原作 朱野帰子 「対岸の家事」2021年06月15日 講談社文庫より出版
TBS ドラマのリンク
https://www.tbs.co.jp/taigannokaji_tbs
魅力的な登場人物
絶滅危惧種!?専業主婦は贅沢なのか?専業主婦の村上詩穂
ドラマの主人公であり専業主婦の村上詩穂は、出産を転機に自分の仕事を退職して、子育てに専念する。過去の経験から、不器用な自分の性格を認識して選択した生き方がだが、子供としかかかわらない日々に寂しさも覚える。
居酒屋店長で家族大好きの村上虎朗
村上詩穂の夫 居酒屋の店長 村上詩穂の主婦になることについて理解を示し、夫婦それぞれが自分の役割を果たして家族を支えていけば良いという価値観をもって、尊重している。大黒柱として家族を支えており、家族が大好きで、特に一人娘を溺愛し、職場でもたびたび娘の話を自慢している
パパの育休の理想とは何か?エリート官僚パパ 2年間の育休中の中谷達也
厚生労働省に勤務する中谷達也は、仕事もバリバリの完璧主義でこなしていたが、次世代のモデルとして育休を取得して子育てに集中する。奥さんも樹里もバリバリ仕事をしていて出張中のやり取りはテレビ会議等でやり取りなど協力してキャリアを両立させている。完璧主義と徹底した育児計画を立てているが、うまくいかない中、村上と出会い「パパ友」になろうとするが価値観の違いでぶつかってしまう。
自転車に2人乗せて全力で毎日働く2児のワーママ 長野礼子
バリバリ営業部で活躍をしていたが、育休後の復帰した部署は総務部だった。 毎日2児の保育園の違う子供を時短勤務を使いながら送り迎えをして、夜子供が寝た後に残りの仕事をする日々。夫は忙しいため、ほぼ礼子が一人で育児と家事をする。子供の体調不良など自分ではどうすることもできないことで周りに迷惑をかけてしまう状況で限界を迎える日々を送る
不妊治療をしながら、子作りプレッシャーに耐える蔦村晶子
娘の掛かりつけの小児科の受付をしている蔦村。もともとは保育士で、跡取りの 蔦村医院の若先生と結婚を機に保育士をやめ、病院の受付をしている。性格も明るく朗らかなため、周りの方に好かれているが、義母や、おしゃべりな一部の患者からの子作りプレッシャーから、不妊治療をしながら過ごしている
専業主婦の先輩 しかし、最近どこか物忘れが多く、、坂上知美
村上詩穂の良き理解者であり、話し相手の専業主婦の先輩 日々の詩穂の話や愚痴などを聞いてくれる、詩穂にとっても安らげる相手 独身で、バリバリ仕事にまい進する娘がおり、娘からは結婚や孫などは期待しないでほしいと言われている。同じものを複数買ってきていることや、万引き疑惑事件が発生してしまい、認知症の疑いが発覚する
ドラマを見た感想(ネタバレあり)
このドラマは、日々子育て世代がぶつかってきている壁を個性的な登場人物の日常として描くことで、改めて壁を「問題」として顕在化させ取り上げることで今までは認識してなかった、もしくは壁のまま体当たりして疲れ切っていた自分に対して共感と励ましをもらえると感じました。
このドラマを見て感じた率直な感想は、「子育て世代に誰にでもある壁」に対して、無意識に孤独に抱え込んでしまっている現代に対して「それは、問題だから立ち止まって疑問に思ってもよい」とメッセージをもらえるような内容だと感じました。
つまり、自分自身で無意識で陥っている「子育て像」や「父親・母親像」、「理想の子育てと仕事の両立」に囚われてしまい、悩んだり苦しんだりする経験を「しょうがない」「自分の力不足」「環境のせい」などで済ませている状況を一種の問題として「顕在化」させてくれているということです。
印象に残った言葉(ネタバレあり)
主婦業を選択することは贅沢なのか?
主婦業を選択した村上詩穂に対して出会ったばかりのパパ友の中谷達也の言葉
「低成長 少子高齢化 養わなければいけない人間が多いのに、この時代に家事だけに専念できる余裕はこの国にはないんです。専業主婦は贅沢です」
「家事は仕事ではない(賃金が発生しないので) 終身雇用制度が崩壊した世の中では共働きを選ぶことでリスクヘッジになる」
「家事」と「給与が発生する仕事」を比べた時に、労働という観点からは家事は認められないという社会的認識と、共働きが当たり前になってきている現代において「家の家事だけをやる」ということに対して後ろめたさを感じさせるような言葉にも感じる内容です。
育休復帰しても子供の病気などで追い詰められるワーママ
育休明けから復帰したワーママの長野礼子が、仕事との両立で自分を追い詰めた時の言葉
家事を片手間にできなかった。手抜きばっかり、寝かしつけして寝るのは1時 毎日その繰り返し、朝が来るのが怖い仕事も家事も両方全部やる それが今の時代では当たり前だし、私は間違っていないでも全然思い通りにできなくて、自分の選択が間違っていたんじゃないか、そう思うと怖かった
仕事は前倒しでやっているけど、子供が体調不良で全部パー 私が休んだ分誰かが肩代わりしないといけない発生した損害を被るのは私じゃない 苦しむのは私じゃない だから苦しい 休むくらいなら最初からいない方がよいのかな
礼子はもともとバリバリのキャリアウーマンであり、子供がいないときは仕事でもハイパフォーマンスを出していた自分ではアンコントラブルな子育ての様々な問題に直面した時に、自分はできると思っていた「理想」とできなかった「現実」に自分自身を追い詰めてしまっていた。正直私自身も働いているので、礼子の気持ちは痛いほど共感できました。
働いている方が楽だった、、子育ては何一つ進んでいる感じがしない
パパ友の中谷達也が、慣れない子育てを通して感じた感想
2か月前までこんなに家事が大変だと思わなかった 働いている方が楽だった すぐ泣く すぐこぼす 日本語が通じない 幼児と二人きりの毎日で精神が精神が蝕まれていく 毎日同じことの毎日で 何一つ進んでる感じがしない 永遠にタイムリープしているのではないかという気持ちになる 一日が長い居場所すらないなんて知らなかった
特に育休中は誰しもがこの問題に直面するのではないかと思います。ちょっと目を離したら命を落としてしまう生き物と一緒に、毎日同じことを繰り返しこなしていく日々。とくに仕事をしていた時は成果をして結果を出すことができたが、子育てにはそれがない。孤独を感じながらも前に進まなければいけないという状況があるということを教えてくれます。
自分たちのロールモデルって誰なのか?時代とともに考える
ロールモデルについての企画で長野礼子が疑問を呈したときに、村上詩穂と話していた内容
会社が、今の時代のロールモデルは、子育てと仕事を両立している女性がふさわしいと言われたことに対して
人生の選択はブッフェのようだ ロールモデルは役割の押し付けではない 一人一人が自分のロールモデルを選べばよい
その時代によっては、「こうあるべき」という社会的な押し付けに合うことが良くあるということを認識させられます。
ちょっと前の時代では、女性は妊娠したら仕事を辞めて家庭に入るべき もしくは、体を酷使してキャリアを優先して結婚子育てをせず昇進する等が当たり前から、今の当たり前は「子育てと仕事の両立」 ただ、それを選択するのはあくまでも自分であり、自分自身がなりたい自分になってよいというメッセージを感じます。
夫婦のキャリアは夫婦で一緒に解決するには対話しかない
子育てに思い悩んで離婚を切り出した中谷達也に対して、奥さんの樹里と話した内容
仕事はその気になれば挽回できるが、家族はそうならない。大事なことほど先延ばしにしてしまう大事なことほどちゃんと話し合うことが必要 お互いを思いやるのが夫婦 夫婦で話して解決するということを、日々忙しくておろそかにしてしまう
誰かに言われると当たり前と思ってしまうのですが、実際に時間をとって真面目に話し合うということは難しい人も多いはず。前に別の記事で書いた、「デュアルキャリアカップル」という本にもありましたが、キャリアを作り上げていくためには夫婦の話し合いは必要不可欠なんですよね。
過去の記事でも紹介中
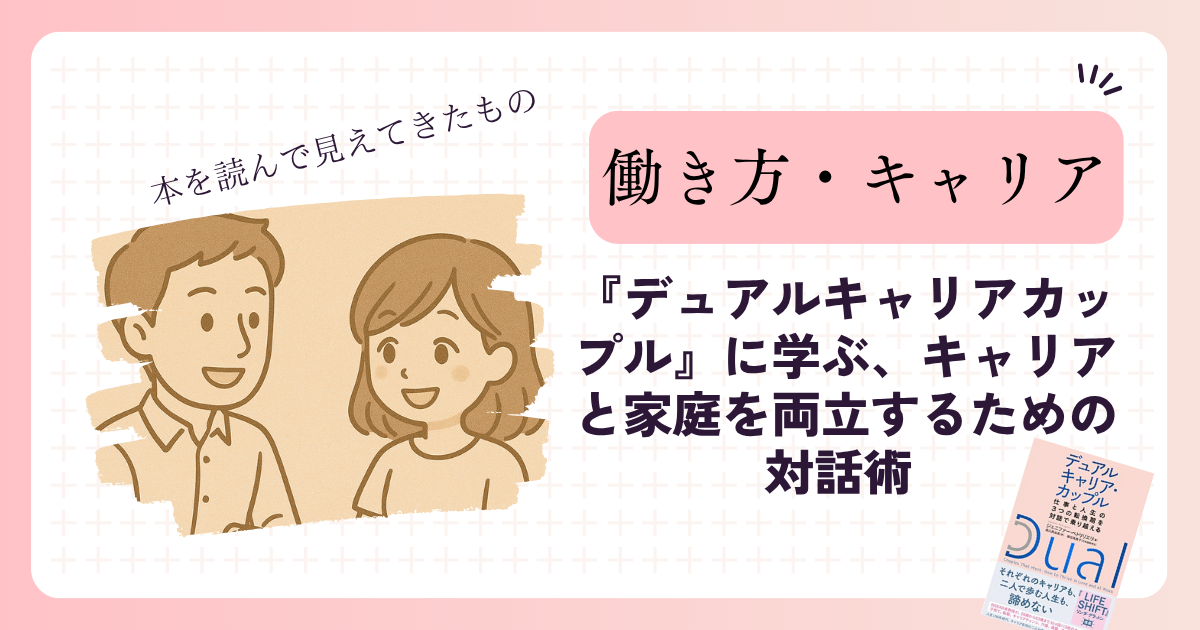
恐れるな子育てとの両立 ドラマを通して伝わってくるメッセージ
対岸の家事は、もともとは「対岸の火事」ということわざから来ており、もともとの意味は自分には関係のない他人の問題やトラブルを指し、まるで向こう岸の火事のように、自分には影響がない、無関係なことだと見なす様子 を意味しています。しかしながら、このドラマでは、誰もが逃れられない終わりのない「家事」に対して、他人事ではなく自分事として何か一つ気づいて上げられれば、そこから世の中はもっと生きやすくなるというメッセージを一貫して発信しているように思います。
私自身も20代のころは目の前の仕事に夢中でそればかり集中してれば良かった日々で、このころの自分はこのドラマに出会っていてももしかしたらそこまで共感できなかったのではないかと思います。
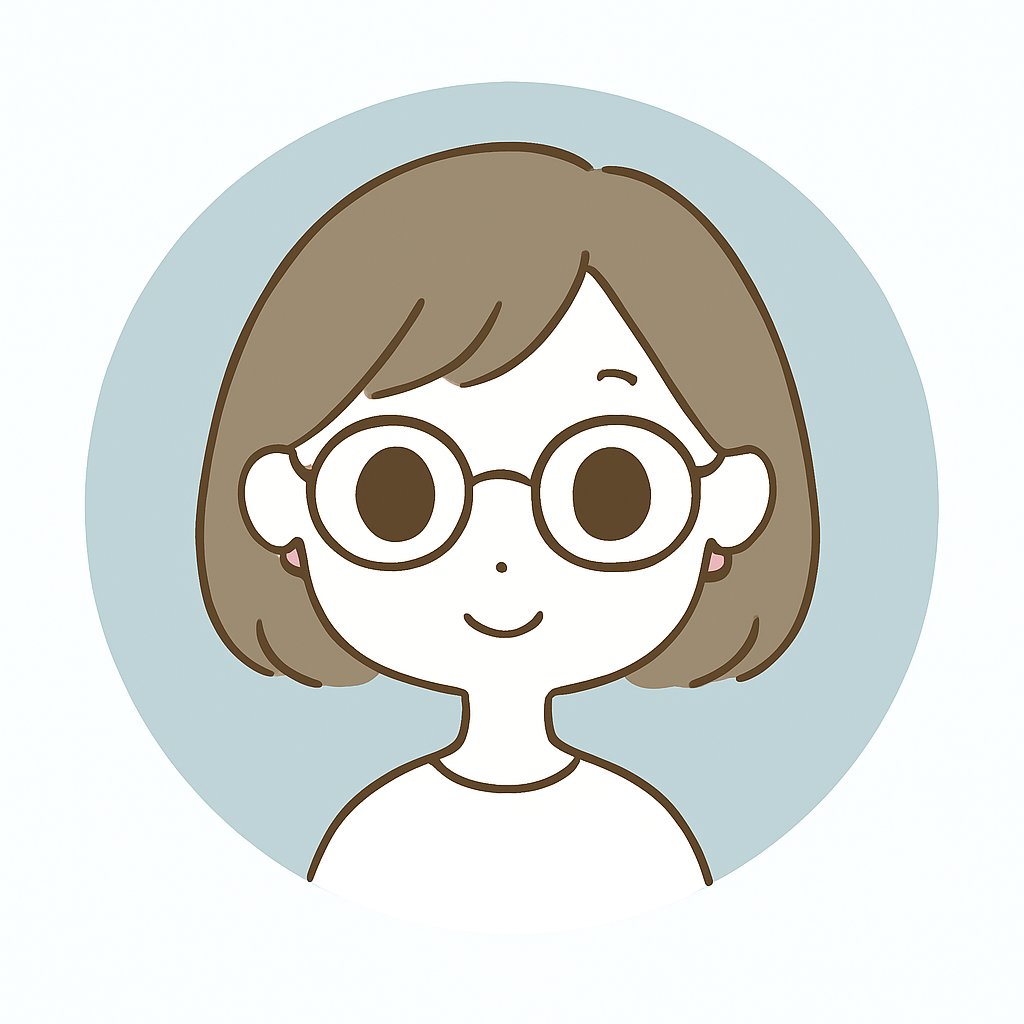
自分事になったとたん共感しかない話ばかり。。独身時代の私はそこまで正直考えられてなかったな。。
当事者となってみて、初めてその人の立場や苦労がわかる。これは子育てに限ったことではないですが、このドラマを支持している層もきっと同じ境遇の方が多いのではないかと勝手に想像しています。
一方で、当事者になるときにまでに対策ができるのか?というと一概には難しい部分もあるかもしれません。
女性の社会進出とキャリア形成、それに伴う晩婚化の世の中を考えると、実際に上記問題に気付けるのは30代以降になってしまうのではないかと思います。
私自身もまさにそのようなキャリアを歩んでおり、2人目の際は40代になる手前でした。ドラマの登場人物のように日々子育てに悩み、仕事の両立に悩み保育園の着信に恐怖を感じる毎日でした。子育ての情報収集は頑張ってましたが、結局思い通りにならないことが多かったです。
ただ、悪いことばかりでもないのも事実です。というのも、30代になるとある程度の社会的仕組の理解、精神的な成熟度、他者への理解も20代のころに比べて進んでいる自分も客観的理解できるときがあります。もちろん日々余裕はないのですが。人は誰しも全能にはなれないということを、ライトに受け止めることが大事だと思いました。
ここで言う「ライトに受け止める」ということも実は重要で、「出来ない=NG」というレッテルではなく、「出来ない=これって無理ゲー(最初からクリアできないゲーム)だから、真っ正面からぶつかってはダメだ」と早々に見切りをつけてしまうということです。
まとめ
本当はいろんなものを頼っていいし、楽したっていいという意味も含めて子育てには「ライトさ」が必要なのかもしれません。
子育てや仕事に迷いながらも、私たちはそれぞれの選択をして日々を生きています。このドラマを通して、「どんな選択であっても、自分の人生を肯定していいんだ」と背中を押されたような気がしました。悩んでいるすべての人に、ぜひ見てほしい作品です。