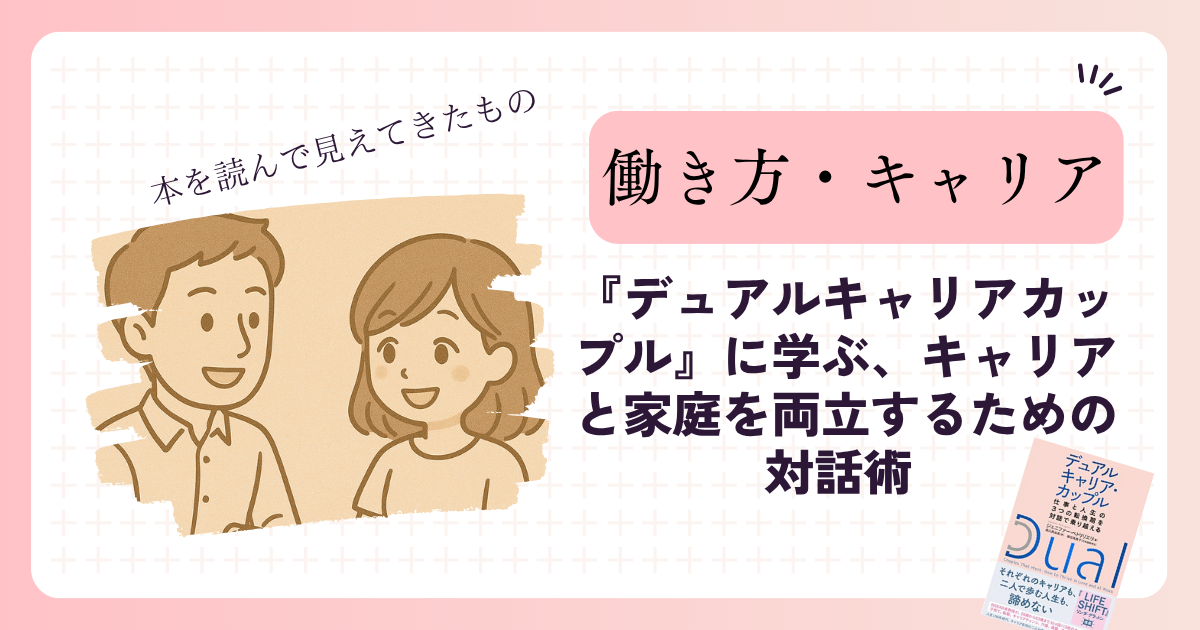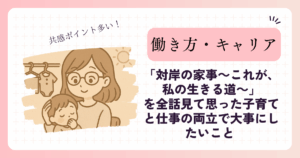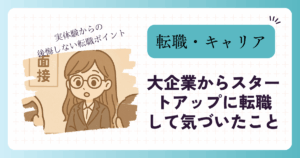はじめに:30代 女性として「キャリアも家庭も」手放したくないあなたへ

30代の共働き女性として、キャリアも家庭もどちらも大切にしたい──。それはごく自然な願いでありながら、現実の中でバランスを取るのが難しいのも事実です。
転職、出産、育児、夫の転勤といった人生の転換期が次々とやってきたとき、どんなに努力していても「もう無理かもしれない」と心が折れそうになる瞬間がありませんか?
今は情報が簡単に入手できる時代なので、受験や就職なども前もって対策はできるのに、女性の人生設計の前もっての対策の難しさを改めて日々感じます。
私自身、結婚、転職、そして夫の異動という波をくぐり抜けてきました。その中でいつも感じていたのは、目の前の選択肢が“今この瞬間”だけを見て選ばれているのではないかという不安でした。長い目で見て、私たち夫婦はどこへ向かっているのだろうか。そもそも、私はどんな人生を描きたかったのだろうか。。
そんな問いに寄り添ってくれたのが、『デュアルキャリアカップル』という1冊でした。
この本は、夫婦というチームが、人生のさまざまな壁にどう向き合い、どのようにお互いの夢を叶えていけるかを説明してくれています。
今からパートナーを見つけようとしている人にとっては予習本であり、すでに結婚生活を送っている人にとっては試練における対策本になるかと思います。
この記事では、本書の概要と共に、私自身が感じたこと・考えたこと、そして「共働き」というライフスタイルを選んだ私たちがこれからの人生で大切にしたいことについてお伝えします。
『デュアルキャリアカップル』とは?
- 書籍タイトル:『デュアルキャリアカップル』
- 著者:【著 ジェニファー・ペトリリエリ/ 訳 高山真由美】
- 出版社:【英治出版】
- 出版年:【2022年3月28日】
- 購入リンク:www.amazon.co.jp/dp/4862762972
「デュアルキャリア・カップル」とは?
「二人とも自分の職業生活が人生において、大切で、仕事を通じて成長したい」と考えている夫婦、カップルのこと
欧米ではすでにこのデュアルキャリア・カップルは夫婦の標準型となっていて、さらに増加傾向であること。また、経済的な理由に加えて、「男女が等しく仕事にも家庭にも積極的にかかわることで充実した人生を送れる」という価値観が主流になっているといわれている
どんな本?
本書は、「自分の職業人生を通じて成長したい」と考えるカップル──“デュアルキャリアカップル”をテーマにしています。
著者はINSEADの准教授であり、世界32カ国、113組の多様なカップル(同性・事実婚・再婚含む)へのインタビュー調査から、「キャリアと家庭を両立する」という現代の共働き夫婦が直面する課題を見出しました。どの国・どの文化でも、ある種共通した”3つの転換期”が夫婦に訪れるといいます。本書では、その3つの”壁”の乗り越え方を、さまざまなケーススタディと共に紹介してくれています。
単なる統計や理論に終始せず、研究による様々な夫婦間のケースを題材に、人間の心の揺れや葛藤を伴った”リアルな選択”の記録が詰まっています。
よく、子育て雑誌であるような、「夫婦間の役割を明確にしよう!」「家事を分担しよう!」といった方法論からもう一歩深いところに踏み込み、お互いの価値観を対話によって共有しあうことの重要性を伝える内容となっています。
共働き夫婦に訪れる「3つの転換期」とは?(ネタバレ含む)
第1の壁:時間と場所の変化による転換期
最初の転換期は、”環境の大きな変化”によって訪れます。たとえば、夫の転勤、どちらかの転職、あるいは初めての出産──。
このとき、夫婦が直面するのは「どちらのキャリアを優先させるか?」という根源的な問いです。表面的には家事・育児の分担をどうするかといった議論になりがちですが、実際はもっと深い価値観の衝突や、将来像のズレが潜んでいることを指摘してます。
本書はこの壁を、単なるライフイベントとしてではなく、「夫婦の対話の質」が試されるフェーズだと説いています。
第2の壁:自身のキャリアに疑問を持つ転換期
次に訪れるのが、ある程度キャリアを積んできたあとに直面する“迷い”です。
「このままでいいのか?」「私は本当にこの仕事を望んでいたのか?」という自問が生まれるこの時期。特に女性にとっては、出産・育休からの復帰後にギャップを感じたり、周囲との差に苦しんだりするタイミングとも重なりやすいです。
夫婦のどちらかがこの”内なる問い”を抱えているとき、その揺れをもう一方がどう受け止めるかが非常に重要になります。本書ではこの時期の対話の在り方にも丁寧に触れています。
第3の壁:人生の後半に向けた再定義
子どもが巣立ち、仕事でも“年長者”としての扱いを受けるようになる──。
この”第3の壁”では、自身のアイデンティティーの空白による、これまでの生き方・働き方をどう意味づけ直すか、そして夫婦の関係性をどう再構築するかが問われます。
今の私たちは何者なのか?という問いに向き合い、将来の可能性を開いたまま、自分たちを刷新していく気持ちの重要性を説いています。
印象に残ったポイント:「キャリアの優先順位」は対話でしか決まらない
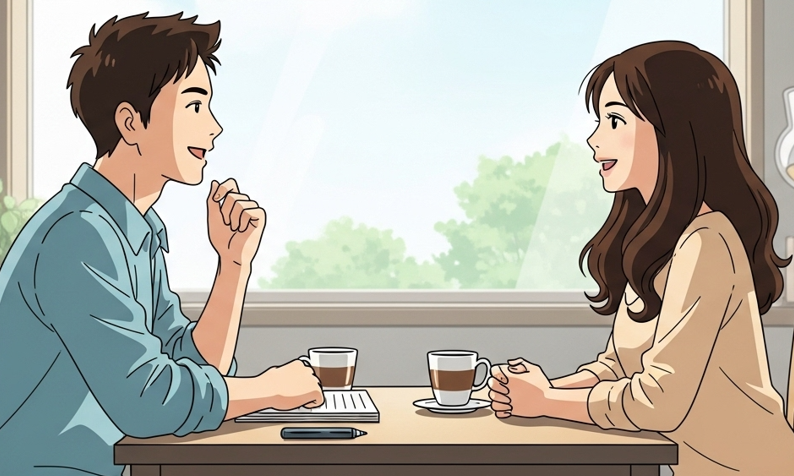
この本の一番のポイントは「夫婦間の対話」にフォーカスされていることです。
例えば、本書のカップルの例にもありましたが、出産を迎えたタイミングと、夫の転職が重なった際に、方法論としては「お互いの家事を分担して、健全な関係を維持すること」ばかりが先行してしまいがちですが、その際の、夫のキャリアへの考え方や、妻の気持ちなどをお互いに深く話し合っていないという指摘されてます。さらに、例えばそれが一方のキャリアを長年我慢させ続け、一方のキャリアを優先することによる弊害や夫婦関係の破綻へ向かうことにつながると指摘をしています。
そして、個人的に最も心に残ったのは、第一の壁で説明させれている「キャリアの優先順位」をどう決めるかという話題でした。
本書では、夫婦のキャリアの優先順位のモデルとして、以下の3つを提示しています。
一番手・二番手モデル
どちらかのキャリアを優先させる デメリット→一度決めると変更しづらい
交代制モデル
定期的に一番手と二番手が入れ替わる
デメリット→交代のタイミングがあいまいになる
両者とも一番手モデル
二人とも一番に優先する
デメリット→一番魅力的だが、明確で強固なお互いの限界を設定して関係を守らないと
すべてやらなければいけないという罠にかかってしまう
最も理想的に見えるのは3番目かもしれませんが、著者は「夫婦間の洗いざらしオープンな話し合いの重要性」を強く説いてます。
これはまさに、今の私自身にも突き刺さる問いでした。私たち夫婦はこれまで、“なんとなく”で決めた役割を当然のようにこなしてきましたが、その先にあるのは無意識の犠牲かもしれないということを改めて意識させられました。
読んで変わったこと:無意識の選択に、自覚を持つようになった
この本を読み終えたとき、過去の自分の選択をいくつも思い返しました。
夫の転勤で退職したこと。転職先でのキャリアを模索する中で、「家族のため」という言葉を自分の背中を押す免罪符にしていたこと。どれも、表面的には円満な選択でしたが、心の奥底では「本当はどうしたかったの?」という声が消えていなかったことに気づきました。
そして改めて、「夫婦間の対話」は、イベントが起きたときだけでなく、何も起きていない日常の中でこそ必要なのだと感じました。
腹を割って夫と話すことが、正直恥ずかしさもあってか深く実行できてなかったので、これからはこの本をきっかけに時間をとっていこうと思います。
女性のキャリアはなぜ”犠牲”になりやすいのか?
本書では、「女性がなぜキャリアを諦めるのか?」についても掘り下げられています。
その背景には、社会的な無意識の期待(=母親は子育てに専念すべき)、職場での非協力的な態度、家庭内の無意識な負担の偏り──など、多くの要因が複雑に絡み合っています。
そして一度キャリアを離れた女性が、再び同等の条件で働くのは極めて難しい。結果として、1人の配偶者が離職することで得られる経済的損失は、100万ドルを超えるともいわれています。
これは決してお金の問題だけではなく、「選択肢を失う」ということがどれほど個人にとって大きな痛手になるのか改めて意識させられました。
こんな人におすすめ
この本は、次のような方におすすめです。
- 共働きで家庭とキャリアの両立に悩んでいる30〜40代の方
- 転職・出産・育休復帰など、人生の転換期にある方
- 夫婦関係を見直したい、再構築したいと考えている方
- パートナーと将来について話す時間が持てていない方
まとめ:キャリアも家庭も、大切にする人生を選ぶために
『デュアルキャリアカップル』は、「キャリアも家庭も、どちらかを諦めなければならない」という思い込みを手放すきっかけになる一冊です。
大切なのは、方法論を追求して正解を見つけることではなく、夫婦で向き合い、語り合い、それぞれの想いを理解しようとするプロセスこそが、かけがえのない未来をつくる鍵になるのだと、この本は教えてくれます。 また、夫婦で向き合うためにも自分自身のキャリアをどうしていきたいか(本書ではキャリアの地図と表現)を深く見つめなおして俯瞰し、向き合う必要があることを再認識しました。
改めて私自身も、これから出会うであろういくつかの壁を目の前にしたときに、「一人で抱え込まない」「無意識のうちに諦めない」選択をしたいと思いました。
※この記事が誰かの気づきや安心につながったなら嬉しいです。
今後も「共働き夫婦」「キャリア」「人生の転換期」に関する書籍レビューや実体験を発信していきます。